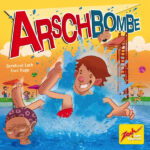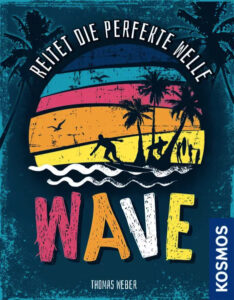
| 発売年 | 2023年 |
| 作者 | Thomas Weber |
| プレイ人数 | 2-4人用 |
| 対象年齢 | 10歳以上 |
ゲームレビュー
「パストニヒト」の陰に隠れた協力ゲーム
あの「パストニヒト」の作者、Thomas Weberが同時期に3作を同時発表していたことをご存知だろうか。そのうちの1作(残る最後の1作はキッズゲーム)が、知る人ぞ知る協力型カードゲーム『ウェーブ』である。「パストニヒト」があまりにも有名すぎて、この「ウェーブ」の存在はあまり知られていない。しかし、「ウェーブ」もまた、Weberの才能が光る、非常によくできた協力型カードゲームなのだ。仲間と協力して、カードの数字と色の”重要度”を考えながら荒波を乗り切り、すべてのカードを出し切ることを目指す。カードの持ち方に工夫がされており、小箱協力ゲームといえば思い出す「花火」に近い雰囲気のゲームに「オーレ!」を足したような流石Weber!という出来になっている。

乗るぜ、そのビッグウェーブに!
ゲームの目的は、波乗りを模して、数字と色のそれぞれに強さの順番が決まっているカードを1人1枚ずつ順番に出していき、全てのカードを出し切ること。よくある協力ゲームのそれだが、このゲームの肝は手札のカードの持ち方にある。配られた5枚の手札を3枚は自分に向けて、残りの2枚は相手に向けて持つ。
この後、色か数字が強くなるように1人1枚ずつ出していく。数字が強くなり過ぎてしまっても色で復活できるし、その逆もできるようになっていて、”永遠に出し続けられるカードゲーム”の称号を戴く名作カードゲームの「オーレ!」に近い感覚がある。
そして、カードを出したら山札から1枚補充する。このカードの向きは、今出したカードと反対向きに手札に加える。つまり、自分から見えるカードばかりを出していたら見えないカードばかりになってしまうので出すバランスが大事。相手にしか見えないカードは他のプレイヤーが見てアドバイスをくれる。相手に見えているカードの情報から、自分が何を出すべきか、あるいは出すべきでないかを判断する必要がある。

手番順が逆回りになるマークがついているカードもあり、これをうまく使ってみんなで波を乗り越えよう。
上級ルール:より高い波が好きなあなたへ
ゲームには元々エキスパートルールも同梱されているが、BGGにも基本ルールしかアップロードされておらず、ドイツ語版を購入すると翻訳に難儀することと思うのでサマリーを掲載しておく。中々の歯応えになるので覚悟して臨まれたい。それぞれを単独で、または他のすべての拡張ルールと組み合わせてプレイすることもできる。
(簡単):チームサーフィン-交換カード
ゲーム準備の際、山札の左隣にさらに1枚のカードを公開する(交換カード)。手番のカードプレイ前に手札のカードを1枚、テーブル中央に公開されている交換カードと交換できる。取った手札は常に自分に向けて持つが、この手番ではプレイできない。その後、手札の好きなカードを交換カードとして場に置く(どちらを向いているカードでも良い、交換カードは内容がわかるように公開して置く)。ゲーム終了まで、常に交換カード1枚が場に公開されている状態となる。交換カードは、ゲーム終了時に捨て札の1番上にプレイする必要がある。
注意: ゲーム終盤で手札が1枚になった場合、交換カードと交換することはできない(プレイできるカードがなくなり、ゲームが終了してしまうため)。
(難しい):潮流の変化
ゲーム中に色や数字の強さが逆転する。プレイヤーは、状況に応じて柔軟に対応する必要がある。この拡張ルールは2種類あり、ここでは別々に説明を記載するが、特別な挑戦として、両方を同時にゲームに取り入れることも可能。

色の強さの逆転:以下のルール変更がある。手札を配った後「色交換」の2枚の特殊カードを裏向きのまま山札に混ぜる。自分の手番で、この特殊カードの1枚目を引いた場合、手札に加えず色の強さの概要カードの上に重ねて、カードを覆う。その後、山札からさらに1枚カードを引き、手札を補充する。これ以降、色の強さは逆転し、青が最も低い色、白が最も高い色となる。この逆転は、誰かが2枚目の「色交換」を引くまで続く。2枚目が引かれたら、両方の「色交換」をゲームから取り除き、ゲーム終了まで通常の色の強さになる。

数字の強さの逆転:以下のルール変更がある。手札を配った後「数字交換」の2枚の特殊カードを裏向きのまま山札に混ぜる。自分の手番で、この特殊カードの1枚目を引いた場合、手札に加えず場に置いておく。その後、山札からさらに1枚カードを引き、手札を補充する。これ以降、数字の強さは逆転し、5が最も低い数字、0が最も高い数字となる。この逆転は、誰かが2枚目の「数字交換」を引くまで続く。2枚目が引かれたら、両方の「数字交換」をゲームから取り除き、ゲーム終了まで通常の数字の強さになる。
注意:もし「色交換」カード及び「数字交換」カードをチーム側に向けて手札に加えてしまった場合、自分自身ではそのことに気づけないので、他のプレイヤーに指摘してもらう。
(非常に難しい):大波
究極のモンスターウェーブに挑戦する拡張ルール。プレイしたカードを捨て札置き場に重ねて置くのではなく、ピラミッド状に並べる。ゲーム開始時、山札の一番上のカードを引き、それを公開して左端に置く。これが最初のカードとなる。最初のプレイヤーは、カードを最初のカードの右隣にプレイする。2番目のプレイヤーは、その上側にカードをプレイする。3番目のプレイヤーは、次の列の一番下にカードをプレイする。このようにして、3列目には3枚のカードが縦に並ぶようにする。これを続けて、各列に1枚ずつカードを追加しながら、6列目が最大の高さになるようにする。その後、高さは各列ごとに1枚ずつ減っていき、10列目で最後のカードをプレイするように置く。
プレイのルール:置く場所に応じて、プレイするカードは場の1枚または2枚のカードより強い必要がある。すなわち、プレイするカードは(もしあれば)常に左隣のカードよりも強い必要があり、同時に真下にあるカードよりも強い必要がある。
この拡張ルールでは、適切なカードをプレイするのは非常に難しい。そのため、特別ルールとして、もしルールに沿ったカードをプレイすることができない場合、自分の手札から好きなカードを選び、それを裏向きに置くことができる。その後、通常通り山札からカードを1枚補充する。裏向きにプレイされたカードは、それは常に他のどのカードよりも弱いとみなされる。最後のカードを場に置いたら、ゲーム終了となる。裏向きのカードの数は、基本ゲームの残りのカードの数に対応する。
ヒント: ルールに沿ってカードをプレイできたとしても、自発的にカードを裏向きに置くことができる。
総評

Bronze
基本的に筆者は協力ゲームに対しては斜にかまえている節があります。なぜなら、協力ゲームである必要のないデザインのゲームが多いからです。1人で遊んでも変わらないもの、つまり、奉行の誕生に立ち会うようなゲーム達に対する評価は辛いです。しかし、このゲームはそのような心配はありませんでした。
このゲームは、手札のカードの持ち方のルールが特殊で、どの向きのカードを出すのかの戦略と他のプレイヤーからのアドバイスのバランスが良いことに加えて、カードをいつまでも出し続けられる色と数字の2重ランク付けが心地よいです。大賞を受賞したボザの「花火」が好きな方は一度遊んでみてください。仲間で波を乗り越える感は確かに味わえます。ヘザーブラウンとか好きな方は、アートも好みかも。